緊張性頭痛予防!自律神経を整える簡単お風呂&入浴習慣法

緊張性頭痛と自律神経の意外な関係
「夕方になるとズーンと頭が重い」「仕事終わりになると頭が締めつけられるように痛む」そんな症状に悩まされていませんか?
それは、緊張性頭痛かもしれません。
現代人に多いこのタイプの頭痛は、首や肩の筋肉の緊張が原因とされており、デスクワークやスマホの使用など、長時間同じ姿勢を取る生活習慣と深く関わっています。
しかし、筋肉のコリや姿勢だけが原因ではありません。
実は「自律神経の乱れ」も、緊張性頭痛を引き起こす大きな要因だということをご存じでしょうか?
自律神経とは?
私たちの体のバランスを保つ“見えない司令塔”のようなもの。
心拍・呼吸・体温・血流など、意識せずに働く多くの機能をコントロールしています。
この自律神経のバランスが崩れると、筋肉が緊張状態から抜け出せなくなり、結果として頭痛が起きやすくなるのです。
特にストレスや疲労、寝不足が続くと交感神経が優位になり、筋肉が硬直したままになりがちです。
逆に、副交感神経が優位になると筋肉がゆるみ、リラックスモードに入ります。
この切り替えが上手くできるようになると、緊張性頭痛の予防・軽減につながります。
毎日の入浴習慣
そこで注目したいのが、毎日の入浴習慣です。
「ただお風呂に入るだけで?」と思われるかもしれませんが、入浴には血流を改善し、自律神経のバランスを整える大きな力があります。
特に、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできるのです。
本記事では、整体師の視点から、緊張性頭痛と自律神経の関係に触れながら、日々のお風呂時間を効果的な“セルフケアの時間”に変える具体的な方法をわかりやすくご紹介していきます。
「頭痛を薬に頼らず、自然に軽減したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
自律神経が整うと頭痛はどう変わる?
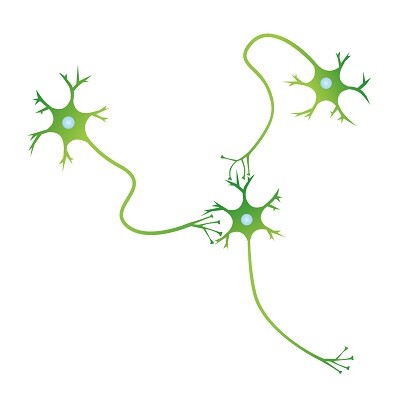 緊張性頭痛の原因のひとつである「自律神経の乱れ」。
緊張性頭痛の原因のひとつである「自律神経の乱れ」。
この言葉を聞いても、「なんとなく身体に悪そうだけど、実際にはどう影響しているの?」とイメージがつきにくいかもしれません。
ここでは、自律神経と頭痛の関係性をわかりやすく解説しながら、自律神経が整ったときに身体にどんな変化が起きるのかを見ていきましょう。
自律神経とは?2つの神経のバランスが大切
自律神経には「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経があります。
【交感神経】
活動・緊張・ストレス時に働く(いわばアクセルの役割)
【副交感神経】
休息・回復・リラックス時に働く(ブレーキの役割)
この2つの神経がバランスよく切り替わることで、体の機能はスムーズに保たれています。
ところが、ストレス・不規則な生活・長時間労働などが続くと、交感神経が優位になりすぎ、副交感神経が働きにくくなる状態に陥ります。
すると筋肉が常に緊張し、血流が悪くなり、肩や首がガチガチに…。
その結果として、頭を締めつけるような「緊張性頭痛」が起こるのです。
自律神経が整うと何が変わる?
では、自律神経のバランスが整うとどうなるのでしょうか?
以下のような変化が期待できます。
- ・筋肉の緊張が緩み、頭痛の頻度や強さが軽減。
- ・血流が改善され、肩や首まわりが楽になる。
- ・眠りの質が良くなり、回復力が高まる。
- ・ストレスの影響を受けにくくなり、心身の安定感が増す。
特に副交感神経がしっかり働くと、リラックス状態が深まり、体の修復・回復モードにスムーズに切り替わります。
その結果、慢性的な頭痛が和らぐだけでなく、再発しにくい体質へと変わっていくのです。
日常でできるバランス調整の第一歩は「入浴」
自律神経を整えるには、生活リズムの見直し、適度な運動、呼吸法なども有効ですが、中でも取り入れやすいのが入浴習慣です。
特に、ぬるめのお湯に10〜15分ゆっくりと浸かることが、副交感神経を活性化させ、筋肉の緊張を自然と解いてくれる効果があります。
整体師がすすめる!緊張をほぐす入浴習慣とは
 緊張性頭痛を和らげたいと思ったとき、薬やマッサージとありますが、まず見直してほしいのが「毎日の入浴習慣」です。
緊張性頭痛を和らげたいと思ったとき、薬やマッサージとありますが、まず見直してほしいのが「毎日の入浴習慣」です。
実は、整体の現場でも、正しい入浴が筋肉の緊張を和らげ、自律神経を整えるセルフケアの基本としてとても重視されています。
ここでは、整体師の視点から、緊張をやさしく解きほぐす入浴のコツをご紹介します。
「ぬるめのお湯」でリラックス神経にスイッチ
緊張性頭痛の原因となる筋肉のこわばりをほぐすためには、熱すぎるお湯ではなく38〜40℃程度のぬるめのお湯に入るのが効果的です。
熱いお湯は交感神経(=緊張のスイッチ)を刺激してしまうため、かえって頭痛を悪化させることも。
ぬるめのお湯にゆったりと浸かることで、副交感神経(=リラックスのスイッチ)が優位になり、心も身体も自然とほぐれていきます。
「リラックスするぞ!」と気負わず、ふぅ〜っとため息をつくような気持ちで入るのがコツです。
入浴時間とタイミングの黄金バランス
理想の入浴時間は15分程度。
長すぎると身体がのぼせて逆効果になることもあります。
また、入浴のタイミングは就寝の1〜2時間前がおすすめです。
この時間帯に入浴することで、体温が一度上がり、その後ゆるやかに下がる過程で自然な眠気が訪れます。
これが、質の高い睡眠と自律神経の調整につながるのです。
「なんとなくシャワーだけで済ませてしまう…」という方も、週に数回でもいいので、湯船に浸かる習慣を意識してみましょう。
入浴前後にやってはいけないこと
入浴をより効果的にするために、避けておきたい行動もいくつかあります。
【入浴前の激しい運動や食事直後の入浴】
血流や胃腸に負担がかかります。
【入浴中のスマホ操作や長電話】
リラックスどころか緊張を助長します。
【入浴後すぐに冷房で体を冷やす】
筋肉が再び固まり、逆効果になる場合も…。
特に、首や肩を急に冷やすと、入浴でほぐれた筋肉が一気に緊張してしまうため要注意です。
お風呂あがりにはタオルなどで軽く首元を温かく保つのがおすすめです。
効果倍増!入浴中にできるセルフケア&リズム呼吸法
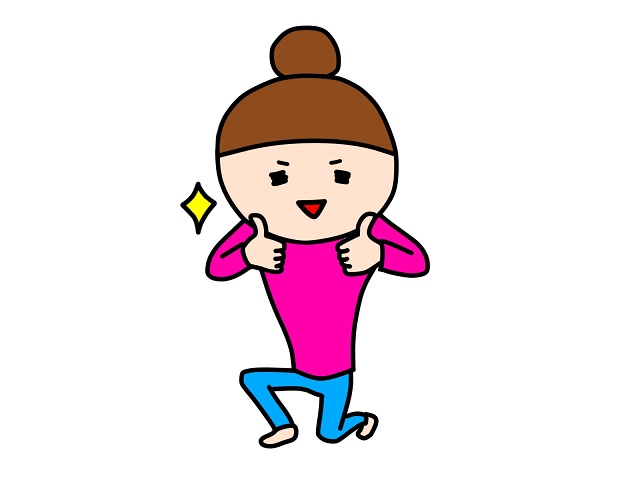 ただ湯船に浸かるだけでも自律神経は整いやすくなりますが、入浴中に軽いセルフケアや呼吸法を取り入れることで、緊張性頭痛の予防・緩和効果はさらに高まります。
ただ湯船に浸かるだけでも自律神経は整いやすくなりますが、入浴中に軽いセルフケアや呼吸法を取り入れることで、緊張性頭痛の予防・緩和効果はさらに高まります。
整体師が現場で実際に指導している、おすすめの方法をご紹介します。
首・肩まわりを温めながら行う軽いストレッチ
湯船の中は筋肉が緩みやすく、ストレッチ効果が非常に高まるタイミングです。
首や肩まわりの筋肉がこわばることで起こる緊張性頭痛に対して、以下のような簡単な動きを取り入れてみましょう。
【首の側屈ストレッチ】
- ・肩までお湯に浸かりながら、ゆっくりと首を右に倒す。
- ・そのまま倒した状態で10秒キープ。
- ・次に左へ同様に行う。
【肩の回旋運動】
- ・肩をすくめるように持ち上げて、後ろに回すようにゆっくり回旋。
- ・前から後ろに5回。
- ・反対回し5回。
【肩甲骨寄せ運動】
- ・両ひじを軽く後ろに引いて、背中で肩甲骨を寄せるように動かす。
- ・5秒キープ×3セット。
これらの動きは湯の浮力によって関節に負担をかけにくく、痛みが出にくい状態でほぐすことができるのがポイントです。
湯船の中でできる深呼吸とマインドフルネスのコツ
緊張性頭痛に悩む方は、無意識に浅い呼吸をしていることが多く、呼吸が浅い=交感神経が優位=筋肉が緊張という悪循環を引き起こしやすくなります。
入浴中におすすめしたいのが、「リズム呼吸+マインドフルネス」。
以下のステップで行ってみてください。
- ・1.肩までしっかり湯に浸かる。
- ・2.目を閉じて、ゆっくりと鼻から4秒かけて吸う。
- ・3.口から8秒かけて吐く(できる範囲でOK)。
- ・4.呼吸に意識を集中しながら、3分ほど繰り返す。
ポイントは、「頭を空っぽにする」のではなく、呼吸の感覚に意識を向けること。
湯の温かさや呼吸のリズムに集中していくと、思考が静まり、自律神経が安定しやすくなります。
このリズム呼吸を毎日続けるだけでも、肩や首のこわばりが和らぎ、頭痛が緩和する方が多いです。
お風呂上がりがカギ!質の良い睡眠で整える自律神経
 お風呂に入って心身をほぐしても、その後の過ごし方によっては、せっかく整いかけた自律神経のバランスが逆戻りしてしまうこともあります。
お風呂に入って心身をほぐしても、その後の過ごし方によっては、せっかく整いかけた自律神経のバランスが逆戻りしてしまうこともあります。
特に緊張性頭痛に悩まされている方にとって、お風呂上がりから寝るまでの「ゴールデンタイム」をどう過ごすかは、予防・改善の大きな分かれ道です。
スマホを見ない・光を落とすなど睡眠環境の整え方
入浴後にスマートフォンやパソコンの画面を見る習慣がある方は要注意。
これらの画面から発せられる「ブルーライト」は脳を覚醒させ、副交感神経の働きを妨げてしまいます。
できれば、お風呂上がりから就寝までは、以下の工夫を取り入れてみてください。
【間接照明や暖色系のライトを使う】
明るすぎる照明は脳に刺激を与えるため、暖かみのある光に切り替えるのが理想的です。
【スマホやテレビの使用を控える】
少なくとも就寝の30分前からは電子機器の使用を避け、本やストレッチなどで穏やかな時間を。
【お気に入りの香りを取り入れる】
ラベンダーやベルガモットなど、副交感神経を優位にするアロマを使うのも有効です。
これらの工夫は、自律神経を自然に睡眠モードへと導いてくれるため、深く質の良い眠りにつながります。
首を冷やさないことで夜間の緊張を防ぐ
意外と見落とされがちなのが、「首の冷え」。
お風呂上がりに髪を濡れたままにしていたり、首元が寒いまま寝てしまうと、体は緊張モード(交感神経優位)に戻りやすくなります。
特に緊張性頭痛は、首・肩まわりの筋肉が冷えて硬くなることで悪化しやすいため、首を温かく保つことが重要です。
【おすすめの対策】
- ・タオルで首を軽く巻いておく。
- ・ドライヤーで髪を完全に乾かしてから寝る。
- ・冬場は首元を冷やさない寝巻きやネックウォーマーを活用。
これだけでも、夜間の無意識の筋緊張が減り、翌朝の頭痛や首こりが軽くなったと感じる方も多いです。
「まとめ」日々の入浴を治療の一環にする意識を
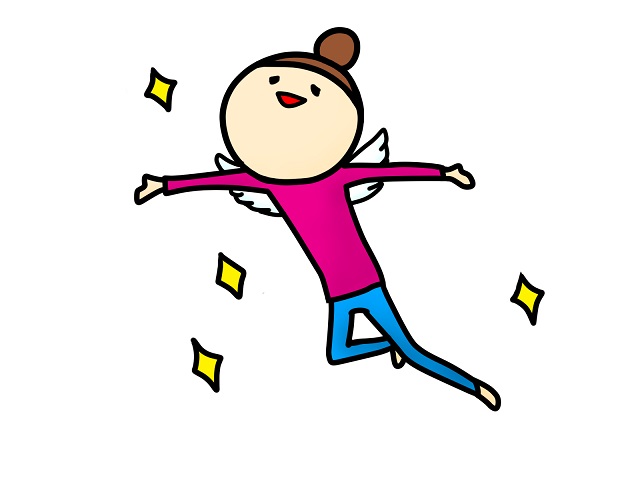 緊張性頭痛に悩む方にとって、毎日の入浴時間は単なるリラックスタイムではなく、症状の予防と改善に役立つ「治療の一環」と捉えることが大切です。
緊張性頭痛に悩む方にとって、毎日の入浴時間は単なるリラックスタイムではなく、症状の予防と改善に役立つ「治療の一環」と捉えることが大切です。
特別な薬や道具がなくても、正しい入浴習慣とちょっとした工夫によって、自律神経は整い、体の緊張もやわらいでいきます。
特別な道具よりも毎日のルーティンが大切
よくある市販の温熱グッズや高価な入浴剤を使わなくても、ポイントをおさえた入浴だけで十分な効果が期待できます。
【たとえば】
- ・ぬるめのお湯(38~40℃)に15分程度つかる。
- ・入浴後は照明を落とし、スマホは触らない。
- ・湯船の中でゆっくりと呼吸し、心身の緊張をほどく。
このような小さな積み重ねを「日々のルーティン」として取り入れることで、無理なく継続でき、体の内側から改善が始まります。
緊張性頭痛の予防は「小さな習慣」から
緊張性頭痛は、ストレス・姿勢・血流の悪化・自律神経の乱れなど、複数の要因が絡み合って起こるものです。
その分、一つの習慣を変えるだけでも体の反応は変わり、頭痛の頻度や重さにも影響してきます。
「今日は疲れたからお風呂はシャワーで済ませよう…」ではなく、「今日こそ湯船でゆっくりして、体と心を緩めてあげよう」そんな意識の変化が、頭痛のない快適な毎日へとつながっていきます。
整体やセルフケアも大切ですが、「入浴」という誰もができる習慣に意識を向けることが、緊張性頭痛の改善において非常に価値ある一歩です。

この記事を書いた人
山田 和也
1974年5月30日生まれ。北九州市小倉南区出身。
【保有資格】
柔道整復師(国家資格)
【経歴】
山口県下関市の整骨院で院長として4年勤務後、地元である北九州市小倉南区で整体院を開業する。臨床経験15年・延べ33450人の施術を行う。(令和6年4月現在)
